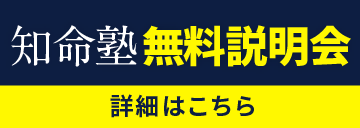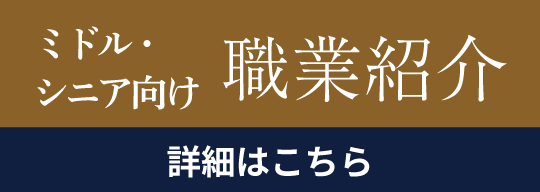「人生100年時代」を迎え、多くの人に60歳を超えても10〜20年現役で働く、新たなキャリア構築が必要とされています。しかし、40代50代といったミドルシニア世代には、いまだ転職に対するネガティブな意識が根強く残っているのが現実です。
こういったネガティブな意識をいかに払拭し、新しいセカンドキャリアの道を探していけるかどうかが、これからの人生の質を大きく左右するでしょう。
そこで今回は、セカンドキャリアの見つけ方を中心に、充実したセカンドキャリアを実現させるための準備や選び方のコツついて、分かりやすくお伝えしていきます。
=目次=
セカンドキャリアとは

セカンドキャリアを見つける前に、まずはセカンドキャリアとは何かを整理しておきましょう。
セカンドキャリアを考えることは、人生を豊かにするきっかけとなります。しかし、ミドルシニア世代が新たにセカンドキャリアを考えることは、簡単ではないケースがほとんどです。
現在の会社以外での経験やスキルに自信がなく、自分自身を否定的に考えてしまうこともあるでしょう。目標はあるのに、なかなか実践できる道筋が見えてこないため、壁にぶち当たることもあるかもしれません。
そこで、一度原点に戻って「セカンドキャリアを考えるようになった理由や目的」をしっかりと定めておくことが大切なのです。
セカンドキャリアを考えること自体が、一歩一歩前に進んでいることだと認識し、諦めずに「第二の人生」を歩んでほしいと思います。
ここでは、セカンドキャリアを考える方が、主に感じている理由や目的をご紹介していきます。
「なぜセカンドキャリアを考えるのか」その軸をしっかりと持ってから、セカンドキャリアの構築に取り組むことがおすすめです。
スキル・キャリアアップ
セカンドキャリアを考える多くの理由は、スキルアップやキャリアアップをしたいという願いからです。
長年同じ会社に勤めていても、なかなか昇格できない。ミドルシニア世代となり意識する「管理職」の立場。これらが、セカンドキャリアを考えるきっかけとなります。
また、これまで勤めてきた仕事はそこそこの知識やスキルが付いてきたため刺激がなく、毎日がマンネリ化している。新たなことを学んで、もっと自分の可能性を広げたい。貯金が溜まってきたから、もともとやりたかったことに挑戦してみたい。
このような理由から、スキルアップを求めてセカンドキャリアを考える方もいます。
ライフスタイルの変化
特に女性に多いのが、ライフスタイルの変化による理由です。
例えば、育児が終了したタイミングで、新しい働き方を考える方もいます。親の介護が必要になり、プライベートの時間を確保しながら、無理のないような働き方を考えるケースもあるでしょう。
結婚から出産、子育てから子供の上京、家や車のローン完済、親の介護など、それぞれのライフイベントの変化に応じて、セカンドキャリアを考えるようになるのです。
ライフスタイルの変化に伴いセカンドキャリアを考えることは、まさに人生を豊かにするための第一歩と言えます。
定年後の不安
定年が近づいてきたミドルシニア世代のほとんどが、定年後の不安を抱えています。このまま定年を迎えれば、退職金や年金があるとしても収入は下がるため、老後の生活費や医療費に不安を感じるのです。
「人生100年時代」と言われていることもあり、できるだけ長く働きたいと思う方が増えています。現在の定年年齢は企業によって異なり、一般的には60〜65歳までに定められていることが多いです。
これまで会社でバリバリ働いてきた人が定年を迎えると、いきなり多くの時間ができた時に、毎日なにをして過ごせば良いのか分からないと戸惑う方もいます。
このような定年後の不安から、セカンドキャリアを検討するのです。
現状の不満
職場の人間関係や労働環境に不満を感じ、セカンドキャリアを考える方もいます。会社の業績が悪化して、リストラを余儀なくされることもあるでしょう。
現状の不満を解決する方法は、状況によってさまざまです。もしかしたら、上司や周りの人に相談すれば解決することもあるかもしれません。自身に何かしらの原因があれば、解決するために努力することも必要でしょう。
しかし、自分自身ではどうにもならない状況もあります。会社の業績悪化は、まさにどうあがいても簡単に経営が回復するわけではありません。
職場の労働環境改善を行うと言っても、実際に環境が変わるのはある程度の時間がかかるものです。今の会社で環境改善における時間を費やすよりも、転職をしたほうが効率が良いですよね。
このように現状の不安や不満を脱却するため、セカンドステップを踏みたいと考える方もいます。
転職を成功させる3つのポイント

セカンドキャリアを充実させるには、定年後も働ける仕事を探して、なるべく早く転職を成功させるのがポイントです。ここでは、転職を成功させる3つのポイントについて解説していきます。
転職する理由を明確にする
40代以降のミドルシニアが転職を決めるには、まず転職する理由を明確にするのが非常に大切です。転職する理由を明確にすると、大きく2つのメリットがあります。
- 転職への強い決意が生まれる
- 転職を成功させるためにやるべきことが明確になる
20代の転職と違い、ミドルシニアの求人は、そもそも絶対数が少ないです。その少ない採用枠をたくさんのミドルシニアが争うので、人によっては何回も不採用が続く可能性もあります。
不採用が続けば、どれほどメンタルの強い人でも、段々と自分の存在を否定される気持ちになってくるでしょう。打たれ弱い人なら、すぐに転職を断念してしまうかもしれません。だからこそ、どんなことがあっても必ず転職するという、明確な転職の理由が必要なのです。
また転職の理由が明確になると、同時にやるべきことも明確になります。ミドルシニアの転職者は、「即戦力としてのスキルと経験」を求められるケースがほとんどです。
現時点で転職条件を満たしていないと自覚しているなら、必要な条件を転職までに急いで身につけなければなりません。
やりたいこと・できることのバランスを考える
ミドルシニアの転職では、「やりたいこと(Will)」と「できること(Can)」のバランスを、よく考える必要があります。
せっかく転職するわけですから、本当にやりたいことをしたいと思うのは当然です。しかしミドルシニアの転職者に求められているのは、前述のとおり、「即戦力としてのスキルと経験」でしたよね。
厳しい話ですが、あなたがなにをしたいかについて、転職先企業はほとんど興味がありません。それよりも、「あなたは自社に対してなにができるのか」に注目しています。
だから自分のなかで、「できることばかり求められるアンバランスさ」にうまく折り合いをつけておかないと、転職活動がひどく苦しいものになるかもしれません。またやりたいことにどうしてもフォーカスしたい人は、おそらく転職もうまくいかないでしょう。
さらにいうと、会社員は自分の希望と関係なく、「やらなければならないこと(Must)」についても考えておく必要があります。
「Will・Can・Must」のバランスのとり方について詳しく知りたいかたは、以下の別記事でご確認ください。
待遇面にこだわりすぎない
ミドルシニアが転職を成功させる1番のコツは、「待遇面にこだわりすぎない」ことです。身も蓋もない話かもしれませんが、待遇面の基準を下げれば、転職の可能性は一気にアップします。
そもそもよほどのスキルや経歴がない限り、ミドルシニア世代が大企業へ転職するのは、ほぼムリだと考えてください。
そう考えると、転職先の中小企業に対して、前職と同水準の待遇を望むほうがムリというものでしょう。繰り返しますが、転職を成功させたいのなら、前職の役職や給与額はひとまず頭から消してください。
その代わり中小企業では、結果を出せば待遇が一気に改善されるケースも少なくありません。転職先での好待遇は、転職後の仕事ぶりで勝ち取ればいいのです。
まずは、「転職先企業に雇ってもらい、セカンドキャリアのスタート地点に立つ」ことに、目的を絞りましょう。
充実したセカンドキャリアのために準備しておくこと

ここまで、転職を成功させるための3つのポイントを解説してきました。ここでは、セカンドキャリアを充実させるために必要な準備を5つお伝えしていきます。
まずは徹底した自己分析から
充実したセカンドキャリアのためには、なんといっても徹底的な自己分析が不可欠です。自己分析で自分が持つ本当の価値や価値観に気づけば、自分が最も望む形でセカンドキャリアを送れる可能性が高まります。
具体的には、まず「自分の市場価値」を正確に分析しましょう。前述のとおり、即戦力としてのスキルと経験を現在の自分が持っているかどうかで、転職の結果は大きく変わります。
もしスキルと経験が不足しているなら、転職の時期を遅らせてでも、まずはスキルと経験の習得に専念するのが得策です。
転職は、業界や職種を変える絶好のチャンスでもあります。これまで培ったキャリア以外の道を進むのも、努力を惜しまなければ決して不可能ではありません。
前述の「Will・Can・Must」に沿って、自分はどういう道を進むべきか、ぜひじっくりと分析してみてください。
キャリアやスキルの棚卸し
充実したセカンドキャリアのためには、キャリアやスキルの棚卸しが必須です。これまでの経験を客観的に把握し、あなたの「強み」を明確にすることで、自分に合ったセカンドキャリアを見つけることができます。
とは言っても、実際にキャリアやスキルの棚卸しはどのように行えば良いのか分からない方もいるでしょう。
現在では、Web検索をするとさまざまなサイトに「棚卸しシート」が掲載されています。自分が取り組みやすいフォーマットをダウンロードして利用するのも一つの方法です。
また、キャリアの専門家に相談することで、自身が今やるべきことのアドバイスを受けながら、自己分析やキャリアの棚卸しに取り組めます。
スキルの棚卸しシートを活用し、これまでの業績や実績を具体的に書き出してみましょう。いきなり「自分の強み」と言われても、ぱっと出てこない方は「自分の長所や短所」から考えてみることがおすすめです。
可能な限り具体的に、詳しく書き出すことを意識してください。
キャリアやスキルの棚卸しは、客観的な目線から行うことがポイントです。キャリアの専門家に相談することで、自分自身では気づかない強みが発見できたり、新たな視点でキャリアを考えられるきっかけとなるでしょう。プロの意見も踏まえて取り組むと、効率的なキャリアの棚卸しができます。
セカンドキャリアに必要なスキルや資格を身に付ける
先程もお伝えしたように、セカンドキャリアに必要なスキルや資格は、転職する前に出来るだけ身に付けておきたいものです。
ただし、スキルはすぐに身に付くものではありません。出来るだけ早く自己分析を行い、じっくりと経験を重ねていくしかないでしょう。
一方資格に関しては、司法試験のような特別に難易度の高い資格でもない限り、長くて2〜3年あれば十分取得できるはずです。
いずれにせよ、必要なスキルや資格の洗い出しも、自己分析の結果をもとに行うのが大前提になります。自己分析が完了していない場合は、なるべく早く着手するのがおすすめです。
会社に依存しない人間関係を構築
多くの場合、会社に勤めている間は、同僚や上司・取引先といった関係性が、社会的ネットワークの中心になります。
しかし、こういった人間関係は、会社という組織に強く依存しており、転職や退職をするとその大半を失ってしまうと考えておくべきです。
いつの時代も、本当に有益な情報は、友人知人からオフレコで伝わってきます。仕事の情報や有力者の紹介も、ある程度信頼関係があるからこそ、便宜を図ってもらえるのです。
したがって、もしセカンドキャリアを成功させたいのなら、会社に依存しない人間関係の構築が必須になります。
もちろん、信頼できる人間関係は、一朝一夕で築けるものではありません。
資格の講習会・地域の集まり・趣味のサークルなど、とにかく気になるコミュニティがあれば積極的に参加してみてください。そこからが、人脈づくりのスタートです。
ただし、いくら人脈が欲しくても、利用してやろうという下心はすぐにバレてしまいます。「楽しく活動していたら、いつの間にか仲のいい人ができていた」という状態を目指し、自然体での活動を心がけていきましょう。
セカンドキャリアの成功はマネープランが必要不可欠
キャリアプランとマネープランは表裏一体。セカンドキャリアで必要なお金が決まらないと、どのようなキャリア(仕事)を選べばいいのか判断できません。
また、セカンドキャリアに必要な金額は、その人の年金額や生活水準・家族構成などにより大きく異なります。つまり、周りの人と同じようにすれば自分も大丈夫だろうという皮算用は、厳禁なのです。
まずは自分たちの生活に必要な金額、中でも趣味や嗜好品を除外した「最低限の生活費」をきちんと把握しておきましょう。
そうすることで、セカンドキャリアでの仕事に求める報酬額が明確になります。条件に合わない転職活動で、時間をロスすることもなくなるはずです。
セカンドキャリアのライフプランニングをしっかりと行いたいという方は、弊社が運営する個人向けキャリア研修【知命塾】をぜひ活用してください。
セカンドキャリアの選び方のコツ

セカンドキャリアの見つけ方は、人それぞれです。趣味や嗜好はもちろん、キャリアに対する考え方も十人十色なので、正解はありません。
ここでは、数ある選択肢の中からセカンドキャリアの選び方のコツをご紹介します。ぜひ、自分自身のセカンドキャリアを考える上で参考にしてみてください。
これまでの専門知識を活かす
まず一つ目は、これまでの専門知識を活かしたセカンドキャリアを選択することです。高い専門性は、どんな企業にとっても即戦力として求められます。
これまで培われた専門知識によって、経験のない業界でも役立つケースは珍しくありません。細かなキャリアの棚卸しを行うことで、具体的にどのような専門知識が自分の武器になるのか見えてくるでしょう。
これまでの実績を活かす
二つ目は、これまでの実績を活かしたセカンドキャリアを選択することです。
実績は、数字や成果として明確に伝えられると良いでしょう。ただし、具体的な数値で示せなくても構いません。小さなことでも、今までの経験がすべて実績として伝えられるからです。
どのような業界で、どのような経験をしてきたか、どのような知識を得て、どのような業務ができるのか。具体的に言語化することで、実績として伝えられることが見えてきます。
やりたいことや好きな分野に挑戦する
三つ目は、やりたいことや好きな分野に挑戦することです。冒頭部分で、「やりたいこと(Will)」と「できること(Can)」のバランスを考えることが大切だとお伝えしました。
そのバランスを考えていく中で頭に入れて欲しいことが「新たな分野に挑戦することは、これまで培ってきた幅広い知識が重宝される」ということです。
新たな分野や業界では、別の観点から物事を考えられる人材を採用し、企業の課題解決や効率的な業務遂行を目指すケースもあります。
ただ「好きなことをやりたい」という考えだけではなく、これまでの経験がどんな場面で活かせるのか紐づけて考えてみると良いでしょう。
挑戦したい分野と自分自身が持つ能力との相性を探すことが、セカンドキャリア成功のコツです。
体力や健康面から取捨選択する
四つ目が、体力や健康面から取捨選択をすることです。例えば、製造業や技能職に携わり現場での業務を行ってきた方が、この先定年まで仕事を続けることを考えると不安に感じるケースもあります。
また、これまでデスクワークを中心に業務を行ってきた方が、いきなり現場仕事に挑戦するといっても、ミドルシニア世代では採用されない可能性もあります。
採用側も、体力や健康面を考慮して検討するため、40代を採用するよりも、長い目で見て活躍してくれそうな若手を選ぶからです。
セカンドキャリアを考える上で「この先10年〜20年後も問題なく同様の働き方ができるのか」を考えることも大切です。
無理のない範囲で、自分に合った働き方を選択するためには、健康面も考慮し検討することが必要なのかもしれません。
具体的なセカンドキャリアの見つけ方

これまでの日本は「ひとつの会社で働き続けるのが美徳」という風潮が根強く残っていました。そのため、現在50代以上の会社員の多くは、転職をほとんど経験していません。
だからこそ、セカンドキャリアを構築する時期がきた際に、どうしていいかわからず困ってしまうのです。そこで、最後に具体的なセカンドキャリアの見つけ方をご紹介していきます。
ロールモデルを見つける
同じセカンドキャリアを実現した方の中で、ロールモデルを見つけると良いでしょう。お手本となる人物像を見つけることで、目指すべき方向性が定まります。
Webを活用してロールモデルとなる著名人を探したり、身近な人から探すのも良いでしょう。尊敬できる人を見つけ、どんな方法で目標達成しているか参考にしてみてください。
ロールモデルとなる人の選択を真似したり、考え方を知ることで自分自身のセカンドキャリアを見つける道しるべになります。
失敗談や困難に打ち勝った経験も知っておくことで、刺激を受けモチベーションが向上するきっかけにもなります。
転職セミナーやワークショップへの参加
セカンドキャリアを見つける方法として、まずは転職セミナーやワークショップへの参加をおすすめします。
転職セミナーでは、企業情報・業界動向・転職市場の最新情報といった、Webでは把握しきれない情報が手に入ります。企業の担当者と直接会話ができるケースも多いので、会社とのマッチングもある程度確認できるはずです。
一方、ワークショップは開催目的によって内容が異なります。弊社が開催する知命塾では、以下のようなワークショップを定期的に開催しています。
- 転職に関する知識のインプット研修
- 自己分析
- キャリア相談
- 転職相談
- 企業経営者や塾OBとの交流会
通常表に出ることの少ない「優良中小企業の情報」や、経営者と直接触れ合う機会を持てるのが、大きな魅力です。
また、このようなイベントに参加すると、同じセカンドキャリアの成功を志す仲間と知り合うことができます。自分の知らない情報も手に入る多いので、ぜひ積極的にコミュニケーションを取っていきましょう。
》》新![知命塾]説明会(個別相談) | 人生100年時代のキャリアづくり-社会人材学舎
インターネットで企業サイトやブログをチェック
インターネットの普及により、以前とは比較にならないほど、転職先について細かいリサーチが可能になりました。中でも、企業の公式サイトやブログは、転職者が必ずチェックすべき重要な情報源です。
企業の公式サイトには、経営理念・事業内容・労働環境・企業の特徴・採用情報など、その企業を理解するための基本情報が掲載されています。
もちろん公式サイトという性質上、悪いことは言わず、良いことばかりをアピールしている面はあるでしょう。しかし、経営者の言葉やサイトの構成などを参考に、おおよその社風は感じ取れるものです。将来その会社でセカンドキャリアを積む自分が想像できるか、じっくりと考えてみてください。
また、ブログやニュースリリースは、企業の日々の活動や取り組み、社風などをよりリアルに伝えてくれます。もし、経営者のインタビューや社員の働き方紹介といった情報があれば、ぜひ参考にしてみてください。公式サイトには書かれていない生の声が聞けるため、より具体的に会社の雰囲気を感じ取れるはずです。
SNSで最新情報をキャッチ
LinkedInやFacebook、TwitterといったSNSは、リアルタイムの情報を得るための強力なツールです。多くの企業は、自社サイトやイベントへの集客を目的に、さまざまな情報をSNSで発信しています。求人に関する情報もSNS経由が多く、今やSNSをやっていないと転職も難しい状況です。
また、SNS(特にTwitter)は、相互コミュニケーションが基本です。不祥事や不適切な対応に対しては、容赦のないコメントやマイナスのリツイートも確認できます。
SNSは匿名での発信のため鵜呑みにはできませんが、ひとつのネガティブな情報として知っておいて損はないでしょう。
なお、SNSの情報は、即時性に重きが置かれるため、不正確な情報が出回る可能性も高いです。情報を活用する際は、信頼できるソースかどうかを確認し、場合によっては複数のソースと照らし合わせて活用しましょう。
キャリアアドバイザーに相談
キャリアアドバイザーに相談して、セカンドキャリアを見つける方法もあります。キャリアアドバイザーは、多くの人のキャリア形成を支えてきた実績があるため、客観的な立場から自分に合った選択をアドバイスしてくれるでしょう。
また、中立的な視点でキャリアに対する悩みの相談を受けてくれるため、最適なキャリアプランを立てられます。長期的なライフプランを立てられることも、プロに相談するメリットの一つです。
キャリアアドバイザーに相談するには、ハローワークや企業のキャリアカウンセリングサービスを利用する方法があります。さらに、個人コンサルタントに直接相談する方法もあるでしょう。
その中でも、転職エージェントに登録するのも一つの方法です。転職エージェントに登録すると、キャリアアドバイザーに相談できるケースが多いため、現実的なセカンドキャリアを構築できるでしょう。
転職エージェントは、転職活動に特化しているため、キャリアプランを一緒に検討してくれるだけでなく、書類作成や面接対策など転職に向けたサポートも行ってくれます。
しかし、ミドルシニア世代がエージェントを活用する際には注意点がありますので、次でご紹介いたします。
ミドルシニアに特化したエージェントの活用
ぜひおすすめしたいのが、ミドルシニアに特化したエージェントを活用することです。転職エージェントならなんでも良いというわけではありません。
先程「ミドルシニアが転職を成功させるには待遇面にこだわりすぎない」という話をしました。しかし、本当に充実したセカンドキャリアを築くには、やはりある程度の役職に就くほうが有利なのも、また事実です。
そのためには、ぜひミドルシニアに特化したエージェントのサポートを活用してください。
例えば、弊社のようなミドルシニアに特化したエージェントの場合、ミドルシニア向け求人が多いのは当たり前。さらには、経営陣としての転職案件も多数扱っているので、よりランクの高い転職が期待できます。
また、一般的にはあまり知られていませんが、ミドルシニア向け転職案件の多くは、転職エージェントのリファレンス(推薦)が必須です。
即戦力を求める企業からすれば、「この人ならミドルシニアの転職市場で十分な価値がありますよ」という転職エージェントお墨付きの人材を採用するほうが、リファレンスがない人よりも安全ですからね。
よって、転職の確率を上げたいと考えるミドルシニアの方は、ミドルシニアに特化したエージェントのサポートを受けるようにしましょう。
まとめ
今回は、転職を成功させて充実したセカンドキャリアを送るための必要な情報をご紹介しました。充実したセカンドキャリアを実現させる方法や、セカンドキャリアの見つけ方についても、しっかりご理解いただけたと思います。
今回紹介した内容はすべて重要ですが、中でも「ミドルシニアに特化したエージェントのサポートを活用する」ことは、転職の成否を決める「転職の生命線」とも言えるポイントです。
自分の棚卸し・転職の準備・実際の転職活動をしっかりと行いたいと考えている人は、ぜひ知命塾のような専門のサポートを活用してください。