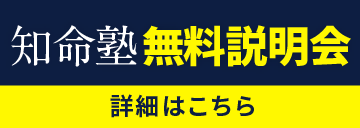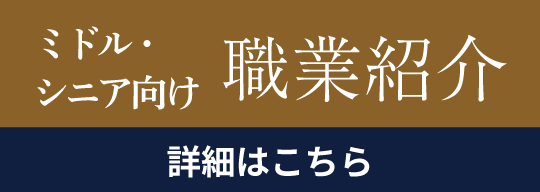「会社人生、このままで本当に良いのだろうか?」
長く働くことが当たり前になってきた現代において、多くのミドルシニア世代が「今働いている会社だけでなく、どこにいっても必要とされる仕事がしたい」と強く願っています。
一方、私たち社会人材学舎グループにキャリア相談をされる方は、
「年齢だけで一次面接さえしてもらえない」
「有名企業の部長までやったのに、紹介されるのはやりがいのない仕事ばかり」
といった悩みを、ほぼ全員が訴えておられます。
詳しく話を聞いてみると、そのほとんどが日々の仕事に多くの時間と労力を費やしており、どんな会社からも求められる人材=社会人材として開花するための活動を、非常に限定された狭い範囲でしかできていないのが現状です。
もちろん、それは決して無駄ではありません。
40代、50代となり責任ある仕事を任されているからこそ、多忙なのは当然です。
でも、そこで思考を止めてしまうと、いつか訪れるキャリアの転機に対応できなくなる可能性があります。
たとえ今の状況が多忙でも、自分の意思さえ明確であれば、自社以外の場所でも活躍できる道は必ず見つかります。
今回の記事では、自社以外の幅広い社会で求められる人材「社会人材」を目指すための具体的な方法について、詳しく解説していきます。
=目次=
なぜ今、あなたは「社会人材」になるべきなのか?

「変化の激しい時代を生き抜く力をつけたい」「自分の市場価値を高めて、今後も安心して働きたい」「より充実したキャリアと人生を送りたい」と感じてはいませんか?
冒頭でもお伝えしましたが、日々の忙しさに追われながらも「このままでいいのだろうか」という漠然とした不安を抱えているミドルシニア世代の方は多いものです。
その不安を解消し、充実したキャリアと人生を築くために必要なのが、「社会人材」になることです。
社会の変化
社会人材を目指すべき理由は、時代と共に働き方が大きく変わったことにあります。
かつての日本では、一度入社すれば定年まで安泰という「終身雇用」が当たり前でした。しかし、今は転職は珍しいことではなくなり、企業も新しい時代に対応できる人材をより積極的に求めるようになっています。
さらに、定年年齢も引き上げられ、私たちはより長く働き続けることが求められています。このような時代に、自分自身が納得して働き続けるためには、会社の枠を超えた力が必要不可欠なのです。
求められるスキルの変化
これからの時代に求められる人材は、求められるスキルの変化に対応できる人です。
AIの普及により、単純作業は自動化され、人間にはより高度なスキルが求められるようになりました。もちろん、長年の経験で培った「仕事の勘」は重要であり貴重です。しかし、それは特定の会社でしか通用しない「社内スキル」の可能性が高いでしょう。
これからの時代に求められるのは、業界や社会が変わっても通用する「ポータブルスキル」です。ポータブルスキルとは、専門的な知識や特定の業界での経験だけでなく、課題解決能力、コミュニケーション能力、マネジメント能力など、汎用性の高いスキルのことを指します。
さらに、特定の分野に特化した専門スキルも持ち合わせていれば、あなたの市場価値はさらに高まります。
これからの時代に求められる社会人材の全体像
「自分にはそんなスキルはない」と不安に感じた方もいるかもしれません。でも、安心してください。誰もが社会人材になれるポテンシャルを持っていますから。
これからの時代に求められる人物像は、「どこに行っても臨機応変に対応してくれる人」です。この人物像を目指すために、自分が持つ強みや経験を「ポータブルスキル」として見つめ直すことが第一歩となります。
ここからは、あなたが社会人材になるために役立つ情報を具体的にお伝えしていきますので、ぜひ最後まで読んでみてくださいね。
あなたが目指すべき社会人材とは

よき社会人材になるには、会社以外でも通用する、幅広いスキルと経験が必要です。もちろん、そういったスキルや経験は、ただ会社で働いていても身につくものではありません。
この章では、「社会で求められる人材」になるにはどういう考え方で行動していけばいいのかを、わかりやすく解説していきます。
まずはどの分野の社会人材になるかを決めよう
一言で社会人材といっても、人それぞれ希望する方向性は異なります。地域との交流に力を注ぎたい人もいれば、貧困や環境など世界共通の課題に興味がある人もいるでしょう。あるいは、新しい仕事を通じて、もっと社会に貢献したいと考える人もいるかもしれませんね。
そう、進む道は人それぞれでいいのです。ただし、どの道を選ぶにせよ、まずはしっかりと自分の方向性を決めてから動き出す必要があります。
なぜなら、最初に「どの分野の社会人材になるか」を決めておかないと、その後の行動がムダになるかもしれないからです。
ただし、途中で方向性が変わっても、それはそれでまったく問題ありません。私も最初は、子どもに野球を教えるだけで満足していました。
ところが野球を教えるうちに、元々教育に興味があり、学校の先生になろうとしていたことを思い出してきます。そんなときに、偶然決まった人材育成部署への異動がきっかけとなり、私は人材育成に関わることを自分のテーマと決めたのです。
このように、動き出してから方向性がチェンジすることも、実際よくあります。これはこれで自然の流れですから、ムリして最初の計画に固執する必要はありません。
いずれにせよ、できるだけムダな行動を減らすためにも、「最初にきちんと計画を立てる」という意識だけは忘れないでください。
どこでも通用する専門スキルを身につける
自分のスキルや経験を、社会的意義のあることに役立て、人に喜んでもらう。これが、社会人材として活動する醍醐味のひとつです。そのためには、やはりなんらかの専門スキルがあると、より深いレベルで活動がしやすくなります。
とはいえ、具体的にどのようにして、自分のスキルを社会人材活動に活かしていけばいいのかがわからないという人も多いはずです。
であれば、自分の専門スキルを活かしたボランティア活動「プロボノ」は、どうでしょうか。
近年では、弁護士や公認会計士・金融・営業・広告・IT系など、プロボノ活動に参加する専門家は増加傾向にあるそうです。自分の専門スキルを発揮できるプロボノなら、一般的なボランティアよりもやりがいをもちやすいというのが、その大きな理由のひとつだと思います。
ただしプロボノはボランティアなので、金銭面での報酬は発生しません。その代わり、机に座って勉強するだけでは決して得られない、「経験」という報酬が手に入ります。
また、会社とは異なるフィールドで活動すれば、普段の生活では出会えない人達との触れ合いも期待できるでしょう。
このようにプロボノは、ほかでは得られない報酬を与えてくれる、非常に有意義な活動です。ボランティアといえども、「いただける対価に見合う成果を提供できるかどうか」を、常に意識しておいてください。
数字・ITなど、基礎的なスキルをベースに
前述のとおり、社会人材には専門的スキルが不可欠です。しかしそれも、数字やIT知識といった社会人としての基礎的なスキルがあってこそ。
もし「お金の動きはよくわからない」とか「IT関連はさっぱりわかりません……」という状況なら、まずはそういったベースとなるスキルを身につけるべきです。
状況に応じて多少の変動はありますが、社会人材を目指すなら、まずは以下4つのスキルから勉強してみてはいかがでしょうか。
- コミュニケーションスキル
- 企画立案スキル
- ITスキル
- タスク / 時間管理スキル
また、社会人に共通して必要とされる「ポータブルスキル」も、しっかりと鍛えておきたいですね。
業種や職種が変わっても使える持ち運び可能な能力「ポータブルスキル」がないと、せっかく多くの専門スキルを学んでも十分に発揮できませんので。
身につけておきたい基礎的なスキルに関する記事はこちらもどうそ
ほかの分野のよい面を柔軟に取り入れる柔軟性をもつ
新規事業成功のコツは、ほかの企業のよいところをマネする「モデリング」だという経営者は多いです。
たしかに、人間誰しも、自分ひとりの発想には限界があります。自分では決して思いつかない第三者のよいところは、どんどん取り入れていくべきでしょう。
これは、ビジネスに限った話ではなく、社会人材に関しても同様です。ほかの分野のよい面を柔軟に取り入れられれば、自分の得意分野と相乗効果が生まれて、さらに多くの貢献ができるかもしれません。
せっかく会社だけの狭い世界から飛び出そうとしているのですから、ぜひ積極的に異分野へ目を向けてみてください。
「求められる人材」になるための具体的なステップ

この章では、社会で求められる人材になるための具体的なステップを3つご紹介していきます。このステップを踏むことで、誰でも確実に「社会人材」を目指すことができます。
自己分析で自己理解を深める
まず第一にやるべきことは、自分自身を深く知ることです。どの分野で社会人材を目指すにしても、すでに持っているスキルと、これから身につけるべきスキルを正確に把握する必要があります。
そのためには、自己分析を行ってください。性格診断ツールを活用するのも良いですし、これまでのキャリアやプライベートを振り返る方法もあります。
また、日々の出来事を日記やジャーナリングとして書き出し、自分の感情や思考を言語化することも非常に有効的です。
自分を見つめ直す作業は、決して簡単なことではありません。自分のことを過小評価したり、逆に過大評価してしまうこともあるでしょう。しかし、この作業こそが、あなたの今後のキャリアを充実させるために必ず役立ちますので。
きっと、新しい自分を発見できるはずです。
自己分析に関しては、次の記事でも説明していますので、ぜひこちらも読んでみてください。
あなたのポータブルスキルを見つける方法
ポータブルスキルとは、特定の会社や職種だけでなく、どこでも通用するスキルのことを指します。これを可視化するためには、診断ツールを活用するのがおすすめです。
インターネットで「ポータブルスキル診断」と検索すれば、さまざまなツールが見つかります。中には、厚生労働省が提供している信頼性の高いツールもあります。いくつかの質問に答えるだけで、自分のスキルを客観的に把握できるでしょう。
また、日々の業務を振り返る自己分析でも、ポータブルスキルを発見できます。例えば、普段の業務スケジュールを書き出してみましょう。
それぞれのタスクをこなすために、あなたがどのような工夫をしたか、どのような計画を立てたか、どのような課題を解決したかなど、行動の裏にある思考やスキルを言語化してみます。
そこには、あなた自身も気づいていなかった秘めたスキルが隠されているかもしれません。
自分の「市場価値」を正しく理解する
自分の市場価値を正しく理解するためには、第三者の視点を取り入れることが非常に重要になってきます。
自分自身が考える自分の価値と、他人から見たあなたの価値は必ずしも同じではないはず。同僚や上司、キャリアコンサルタントなど、必ず自分以外の誰かに聞いてみてください。
客観的な意見を聞いてみることで、自分の強みや弱みをより正確に把握できます。他人に頼ることは、市場におけるあなたの価値を正しく理解するためのポイントです。
人生100年時代に必要な「社会人基礎力」を身につけよう

これまでほかの記事でも繰り返しお伝えしているように、これからの日本は「人生100年時代」がスタンダートになっていきます。
この人生100年時代を踏まえ、厚生労働省が提唱しているのは、「人生100年時代の社会人基礎力」という考え方です。
この章では、この社会人基礎力を構成する3つの力と、社会人基礎力のリカレント教育を提供している「知命塾」について解説していきます。
- 前に踏み出す力
- 考え抜く力
- チームで働く力
- 組織の外でも活躍できる人材を目指して「知命塾」を活用
それではひとつずつ見ていきましょう。
前に踏み出す力
指示されたとおりに動けばいい新人時代と違い、社会に求められる人材ともなれば、「一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力」が求められます。
前に踏み出す力に必要な要素は、以下の3点です。
- 主体性:変化に前向きに対処する力
- 働きかけ力:他人に働きかけ、周囲を巻き込む力
- 実行力:目的を設定し確実に行動する力
近年は時代の流れがとくに速くなり、今正しいと思われる方法が、1年後も正解だとは限りません。だからこそ、まずは変化へ前向きに対応して周囲を味方につけ、自分が主体となりドンドン実行していく「前に踏み出す力」が必要なのです。
考え抜く力
さきほど説明した「前に踏み出す力」は当然必要だとしても、現状に疑問をもち、行動を起こす前にじっくりと「考え抜く力」も非常に重要です。
経済産業省が定めた具体的な「考え抜く力」とは、以下の3点になります。
- 課題発見力:現状を分析し目的や課題を明らかにする力
- 計画力:課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力
- 創造力:新しい価値を生み出す力
ものごとをスムーズに進めるには、まずクリアーしなければならない課題を発見する必要があります。また、見つけ出した課題をいかにクリアーしていくか、実際の計画に落とし込む「計画力」も欠かせない能力です。
しかし、ただ課題をクリアーするだけでは、新しい価値観を生み出すことはできません。ネットで検索すれば簡単に答えが見つかる時代だからこそ、ほかとは違うオリジナリティ(創造力)が、これからの時代には必要なのです。
チームで働く力
チームで働く力は、以下の6点から構成されています。
- 発信力:自分の意見をわかりやすく伝える力
- 傾聴力:相手の意見を丁寧に聴く力
- 柔軟性:意見の違いや相手の立場を理解する力
- 情況把握力:自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力
- 規律性:社会のルールや人との約束を守る力
- ストレスコントロール力:ストレスの発生源に対応する力
前述の「前に踏み出す力」と「考え抜く力」が3要素ずつだったのと比べて、「チームで働く力」だけは、6要素もあります。それだけ、他者とのコミュニケーションはむずかしいということでしょう。
社会人材になるには、自分だけがうまく行動できてもあまり意味がありません。周囲の仲間と協力しながら、ものごとを進めていく姿勢が重要です。
そのためにはまず、自分が属するグループメンバーにしっかりと自分の意見を伝え、同時にメンバーの意見にもきちんと耳を傾けましょう。
時には、意見が対立する可能性もあります。しかしそういう場面でも、決して相手を否定せず、相手の立場をしっかりと汲み取る柔軟性が必要です。
また、グループ内だけの活動では、十分な社会活動はできません。そのため、仲間内以外の多様な人々ともきちんと協調していく姿勢が求められます。
組織の外でも活躍できる人材を目指して「知命塾」を活用

社会人材として必要な基礎力を学ぶには、独学ではなかなか厳しいものがあります。そこでぜひ活用していただきたいのが、弊社が運営する、個人向けキャリア研修「知命塾」(ちめいじゅく)です。
知命塾は、「社会人材式キャリア支援プログラム」の講義&ワークショップ部分に含まれています。
知命塾に参加すれば、経験豊富なアドバイザーや共に参加する仲間の力を借りながら、客観的な視点から自分のキャリア戦略を構築できます。
じつは上図のとおり、「⼈⽣100年時代の社会⼈基礎⼒」育成のリカレント教育機関として、「知命塾」も経済産業省の活動に協力いたしております。
ほかにも教育機関はありますが、知命塾の場合、キャリア構築と再就職支援までをワンセットで提供しているのが大きな特徴です。
新しい仕事を通して社会に求められる人材を目指したいという人は、ぜひ再就職支援も含めた知命塾のプログラムを活用していただければと思います。
「求められる人材」として活躍するためのマインドセットとコツ

ここまで、社会で求められる人材になるための具体的な方法をお伝えしてきました。自己分析を通じて、自分の理想と現実のギャップに不安を感じた方もいるかも知れません。
しかし、足りない能力やスキルがあるからといって、落ち込む必要はありません。求められる人材になるための道のりは、一度にすべてを習得するようなものではないのです。
これからの時代に求められる人材として活躍するために、ぜひ覚えておいてほしい3つのマインドセットとコツをお伝えします。
完璧を求めないマインドセット
「すべてを完璧にこなそう」なんて思っていると、行動に移すことが難しくなります。社会人材になるための道のりは、一度にすべてを習得するものではありません。焦らず、一歩ずつやっていけば大丈夫です。
例えば、「新しいスキルを学んでみる」「キャリア相談をしてみる」など、まずは小さな一歩から始めてみましょう。大切なのは、実際に行動に移してみることです。完璧でなくても、少し前の自分より前進していることを認めてあげてくださいね。
この積み重ねが、やがて大きな成果につながるでしょう。
長期を見据えたキャリアプラン
今すぐの結果だけにとらわれず、長期的な視点でキャリアを考えることが大切です。社会人材になることは、マラソンのようなものです。ゴールまでの道のり全体を想像して、無理のないペースで進む計画を立てましょう。
3年後、5年後、10年後、20年後、自分がどのような場所で、どのような役割を担っていたいかを具体的に想像してみてください。
それを叶えるためには、この1年間で何をすべきか、この半年で何を身につけるべきか、といった短期的な目標も明確になります。
長期的を見据えたキャリアプランを持つことで、日々の努力が「点」ではなく「線」になり、モチベーションを維持しやすくなります。
専門家からの的確なアドバイス
自分一人で悩みを抱え込む必要はありません。自分の市場価値を正しく理解し、効果的なキャリアプランを立てるためには、専門家の力を借りることも有効な手段です。
私たち社会人材グループでも、多くのミドルシニア世代の方々のキャリア相談に乗ってきました。私たちの「キャリア支援プログラム」では、明確な手法やフレームワーク、体系的なプログラムによって、戦略的にキャリアの目標達成を導きます。個人に合わせた課題や行動計画を見直し、戦略を実行して振り返りを行いながら、一緒に理想のキャリアを目指していきましょう。
また、キャリア支援プログラムを受講した方はアルムナイへの参加が可能です。アルムナイネットワークによって、新たな人脈を形成できるきっかけとなるでしょう。
漠然とした将来への不安がある方は、ぜひ、将来のキャリアづくりに目を向けてみませんか。
まとめ
今回は、「社会に求められる人材」に必要なスキルや考え方について、詳しく解説してきました。
なかでもすべてのベースとなる「社会人基礎力」は、ぜひ身につけていただきたい能力です。しかし前述のとおり、社会人基礎力を独学で習得するのは、正直いってかなり大変です。
弊社が運営する「知命塾」などの専門教育機関をうまく活用して、効率よく社会人基礎力を身につけていきましょう。
知命塾についてさらに詳しい情報を知りたい人は、下記の「無料Web相談会」にてご確認ください。